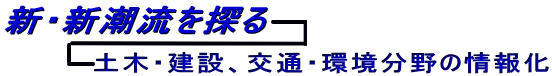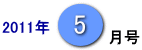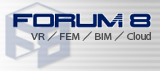�@�v���[���e�[�V�����̖`���A�X�E�H�[�c���͌��z�ɂ��čl����ہA�������̂ł͂Ȃ��A��Ԃ������Ƃ����ϓ_�������B
�@���̏�ŁA3D��Ԃ̓_��2D��Ԃ̖ʂȂLjقȂ鎟���̊w�I�`��igeometry�j�ɒ��ڂ���B�قȂ�^�C�v�̋�Ԃɂ͕����^�C�v�̃I�u�W�F�N�g������A�����̋�Ԃł͊w�I�`��݂̂Ȃ炸�A�d���ȂǕ����I�Ȑ����imateriality�j���l�������B����ɁA��ԓ����ړ����鎞�Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɐ�����ω����l������B���̍ہA�����I�Ȑ����⎞�ԂƂ������v�f����Ԃ݂̂���͂���̂Ɣ�ׁA�����̍���𑝂����Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B����䂦�A�r�W���A����́ivisual analysis�j�̂قƂ�ǂ��w�I�`��̖ʂɃt�H�[�J�X����`�ɂȂ��Ă���A�Ɛ�������B
�@�����œ����́A1930�N�ォ��50�N��ɂ����đ������݂�ꂽ�l�ԂƗގ������]�����l�Y�~�irat�j���g���������⌤���ւƘb��W�J�B�����������ʂ̈�Ƃ��āA�G�h���[�h�E�g�[���}���iEdward Tolman�j���uCognitive Maps in Rats and Men�i�l�Y�~�Ɛl�Ԃɂ�����F�m�n�}�j�v�i1948�N�j�̒��Ō��y�����A�l�ƃl�Y�~�̋�ԂɊւ���m�̗͂ގ����ƔF�m�n�}�iCognitive Maps�j�̔��z�ɒ��ڂ���B�����ł́A����������Ԃƌ������������A�S�̒��ɂ̓x�N�g���̏W�����\�������B����A�������̔]���ɂ͓d�C�p���X��ʂ�3D�̃x�N�g����~�ς��鐶���w�I�\��������Ƃ���B
�@�܂�A�������̐S�̒��ɂ͐��E�n�}������A3D��]���̊C�n�ɒ~�ς����B����ɑΉ������ԉ�͎�@�̈���A�����̐��w�I�v�Z�����I�ȃe�N�j�b�N�inon-discursive technique�j�ŁA���܂��܂ȃ^�C�v�̃I�u�W�F�N�g�������ɊW���������͂�����́B�����́A�݂��ɗׂ荇��2�̃I�u�W�F�N�g�����܂��܂ȃm�[�h�}�inode diagram�j�������A�����̃u���b�N�iblocks�F�X��j�����ꂼ��ŏ����قȂ�A���̎d���Ŕz�u������A����ѕ����̃u���b�N�����l�ȘA���̎d����`��������B����Ɋe��̏��A���邢�͂��܂��܂ȋ�Ԃ��ǂ̂悤�ɑ��݂ɘA�����Ă��邩����������Z�p���g�����A�r�W���A����͂��ԉ�͂ւ̃A�v���[�`�ɂ��G���B
�@�@�@�@ �i���y�[�W�֑����j
�W���[�W�A�H�ȑ�w ���z�w��
������
�}�e�D�[�E�X�E�H�[�c ��
Matthew Swarts,
Research Scientist, College of Architecture, Georgia Institute of Technology
�i�ʐ^�͇��t�H�[�����G�C�g �j
(Photo provided by FORUM8) |
 |
�@�W���[�W�A�H�ȑ�w�iGeorgia Institute of Technology�j���z�w���������̃}�e�D�[�E�X�E�H�[�c����2010�N�x�́uWorld 16�v�v���W�F�N�g�ɂ����āA3D���A���^�C��VR�iVirtual Reality�j�\�t�gUC-win/Road�ŋ�ԉ�́ispatial analysis�j���s���v���O�C���iplug-in�j�̌����Ɏ��g�B
�@��̓I�ɂ́AUC-win/Road�̃A�v���P�[�V������I�v�V�������쐬�ł���UC-win/Road SDK�i�J���L�b�g�j���g���ADelphi 2007 �Ńv���O�C�����J���B���̃v���O�C����ʂ��AUC-win/Road�̋�ԉ�͐��\�傳���A�����Ă��̉�͌��ʂ��������悤�Ƃ̖ڕW���ʒu�Â���ꂽ�B
�@����̃C�}�W���E���{�iIMAGINE Lab�j�ł́A��w�L�����p�X�̃n�C�t�@�C�����A���^�C����3D�����\�z�B�����̃��f���̓L�����p�X�̉����ƂƂ��ɁA��ԉ�͂̌����ɂ����p����Ă���Ƃ����B
Exploring New Trends: Information-oriented Strategy and Technologies in
Civil Engineering, Construction, Transportation and Environment
��ԉ�͂̑��l�ȃA�v���[�`
�r�W���A����ԉ�́iUC-win/Road��
�_�Q�̉�����ʂ��Ď��������Isovist��́j
Isovist Analysis Realized through Point Cloud Visualization
in UC-win/Road
�f�ڋL���E�ʐ^�E�}�\�Ȃǂ̈�@�Ȗ��f�]�ڂ��ւ��܂��B
Copyright©2011 The WrightingSolutions Ltd. (http://www.wsolutionsjp.com/) All rights reserved.
By �r�엲�iTakashi IKENO�j
�i�f�� 7/7/2011�j